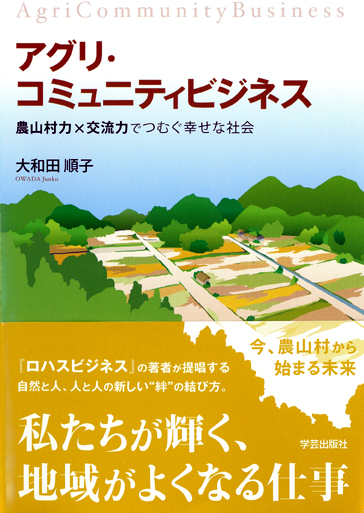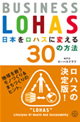2008年05月17日
大分県竹田市、食育ツーリズム雇用創出大作戦!
ついに手づくり味噌ができあがりました!
◆ 念願の竹田での味噌づくり
昨年10月にうかがって以来、すっかり大好きになってしまった大分県竹田市です。
その時に、道の駅で買った味噌の味が忘れられず、今年2月に再び竹田にうかがい、味噌づくりに参加したのです。待つこと3か月。ついに、今朝、味噌だる(といっても、蓋付きポリ容器に密閉しておいただけですが)を封切りし、初ものをいただきました。
味噌を作っている過程。味噌玉をしっかり詰めました
できあがった味噌!
3か月すれば食べられますよ、とお聞きしていましたが、確かに味噌の匂いがします。
ただし、まだ色は浅く、麹のつぶつぶも残っているのもご愛嬌ということで。
「しんの実」(味噌汁の実の意味。千葉県の農家で使われている)は、成城のマイ畑で昨日とれた小松菜とマイタケ(つくばの直売所「みずほの村市場で購入)で。
味は・・・・やっぱり、去年10月に地元で買ってきたおばあちゃんの味噌とほぼ同じ味がしました!おばあちゃんの指導の元、地元の無農薬大豆、無農薬米麹、そして国東の塩。素材はただそれだけです。
こんな面白いものもあります。元祖インスタントみそ汁の素。
お湯をかけて、味噌を溶けばできあがり
無添加、ダシ入りの味噌が一人前づつ小さな玉になっています。
◆ 竹田のまちづくりは「竹田研究所」から始まった
味噌話はここまでにして、本題も竹田のまちづくりについては、ここからです。
まず、まちの概要ですが、大分県竹田市は、九州の中央に位置し、2005年4月に竹田市、萩町、久住町、直入町の四市が合併し、現在の人口約28,000人、面積478平方キロのまちです。
北に阿蘇くじゅう国定公園、南に祖母傾国定公園があり、城下町の歴史文化、竹田湧水群、長湯(旧直入町)の炭酸泉、久住高原、萩の農業観光地など個性ある4つのエリアから構成されています。交流人口は年間400万人を超える大分県内有数の観光地でもあります。
今から10年ほど前、1996年に「竹田研究所」という官民連携の組織が作られました。これは、竹田市観光振興計画(1996年制定)のもと、計画推進委員会の付属機関として設立されたもので、地域の文化・観光資源などの掘り起こしや、農林業・商工業の推進、情報発信などを多角的に行ってきました。
行政職員(10人)と市民研究員(9人)で運営されている組織で、地域再生のリーダー機能を担っています。当初から、「城下町としての歴史的な文化遺産や、恵まれた農村の自然を活かし、市全体を観光の博物館として捉え、訪れる人々に市民の生活と環境を見てもらいながら体験してもらう」という「エコミュージアム構想」を掲げ、商業・農林業・観光を三位一体でまちの振興を行っていこうという考えで活動を行ってきました。
その成果が、観光面では竹を活かしたイベント「竹楽」(ちくらく)であり、食文化面では江戸時代後期の南画家、田能村竹田(たのむら ちくでん)が愛した竹田田楽や、岡藩の食卓を彩った青大豆の復活や、伝統の「家庭料理大集合」というイベントなどの取り組みです。

「竹楽(ちくらく)」 (写真:竹田市観光協会)
<地域活性化のポイント>
1.観光:商工観光課が中心となり、竹を活かしたイベント「竹楽(ちくらく)」を実施。国土交通大臣賞受賞。入田地区に広がり、5カ年で日本一美しい里づくりをめざし、桜と紅葉一万本の植え付けを行っている。
2.農業:九重野地区では、全国初の集落協定が結ばれ、農業の六次産業化をめざしている。「竹田市わかば農業公社」のマネジメントにより、農産物の加工品、道の駅や県内の流通業での販売などが行われている。
3.食文化:「竹田研究所」が中心となり、スローフード運動を提唱、竹田田楽の復活、主婦層が家庭の料理を持ち寄る「家庭料理大集合」等に取り組んでいる。
◆ 昨年10月にスタートした「竹田食育ツーリズム雇用創出大作戦」
こうした幅広い取り組みが認められ、2007年9月、厚生労働省による改正地域雇用開発促進法に基づく「地域雇用創造推進事業(新パッケージ事業)」の2007年度第1次採択分として、32地域の事業構想の一つとして「竹田市食育ツーリズム雇用創出大作戦」が採択されました。
新パッケージ事業とは、昨年の通常国会で成立した「改正地域雇用開発促進法」(2007年8月4日施行)に基づく、地域再生に取組む市町村などに対する支援の一環として、地域の創意工夫により行う雇用創造の推進を図ることを目的に、今年度から新たに実施するもの。委託費は1地域あたり2億円が上限で、事業期間は最長3年です。
ちょうど最初に竹田市を訪問した昨年10月24日は、この新パッケージ事業のキックオフミーティングが竹田地域で開催される日で、記念すべき「新パッケージ事業講演会」(竹田市経済活性化促進協議会主催)に参加することができました。
100人近い市民や事業者、自治体関係者が一堂に会し、熱心な議論が交わされました。
「竹田市食育ツーリズム雇用創出大作戦」は、同市の質の高い水、城下町を中心に発達した「発酵文化」や豊かな自然資源、文化遺産などを主体とする観光産業と、地域の食・産品開発を合わせた食育ツーリズムによる雇用創出を目指すこととし、業種別研修会の実施などを通じ、食育ツーリズムや食づくりを担う人材育成を進め、地域における雇用機会の増大を図るものです。
竹田市は産業面では農業を基幹産業としていますが、他の農山村地域同様、高齢化や後継者不足にあり、また製造業では、地理的条件や交通条件に恵まれないことから企業進出も少なく、就業の場を確保することが大きな課題となっています。
計画では、これら自然資源、文化遺産等を主体とする観光産業と、地域の食・産品開発を合わせた食育ツーリズムによる雇用創出を目指すこととし、業種別研修会、商品開発、販路拡大等の研修会を通じ、食育ツーリズムや食づくりを担う人材育成を進め、地域における雇用機会の増大を図り、2010年3月までに195名の雇用を創出することを目標としています。
この計画は県外のコンサルタントなど第三者が作ったものではなく、地域の人々(観光課の担当者をはじめ、地元事業者、市民、県職員や市職員の有志ら)により作られたこと、そして「竹田市食育ツーリズム雇用創出大作戦」を実質的に担っていくのが、県内で活動する「食育ネット」というボランティア組織だということが極めて重要で、成否の鍵になると私は見ています。
「食育ネット」は、県の職員が2004年に立ち上げたもので、今では県内、特に竹田市や大分市を中心に30人(女性20人、男性10人)がメンバーとして活動に参加し、「子どもたちの未来に希望を作る」を合言葉に、人から人へと緩やかにつながる顔の見えるネットワーク作りを進めています。
メンバーの職業は県や市の職員、企業に勤める人、ジャーナリスト、栄養士、主婦など幅広く、趣旨に賛同した人たちです。ワクワクする取り組みが多くの人たちの賛同を得るという考えのもと、県や竹田市、コープ大分などの食育関連の様々なイベントの企画・運営にあたっています。メンバーの多くは、「大分食育コーディネーター」として県の認定を受け、家庭や地域等における自主的・自立的な食育活動を推進しています。
◆ ワクワクしながら、どんどん色々なプロジェクトが進んでいます
2月の訪問時は、「食育ツーリズム大合同研究会」が開かれました。市長をはじめ、大丸旅館のオーナーで県議の首藤勝次さんや関係者の皆様が一堂に会し、私も「ロハスとまちづくり」をテーマに基調講演させていただきました。その後、各プロジェクトの進捗状況を共有するとともに、試食会でおおいに盛り上がりました。美味しいものが沢山!本当に素晴しい宝が沢山ある竹田です。
「竹田らしさフォーラム」家庭料理大集合。例えばシイタケ寿司 (2008年2月)
味噌造りの後は家庭料理を持ち寄って昼食。(2008年2月)
※プロジェクトの進行状況は以下のWEBサイトでごらんいただけます。
http://taketa-syokuiku.org/menu.html
Writing: owadajunko